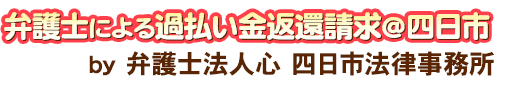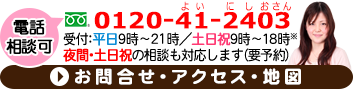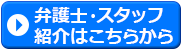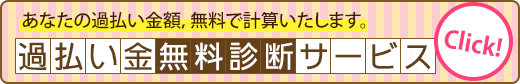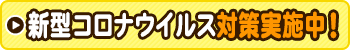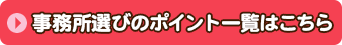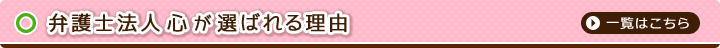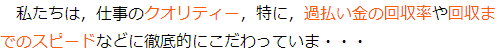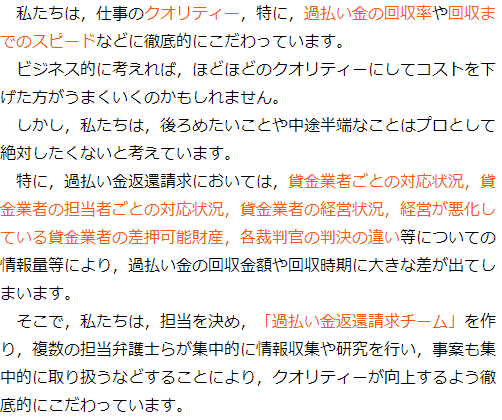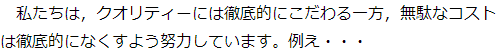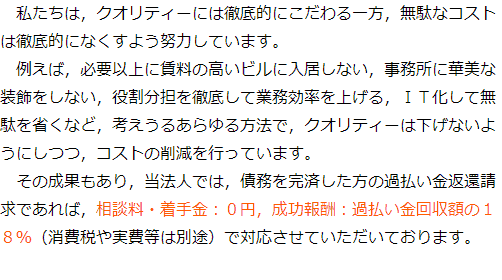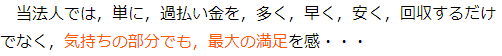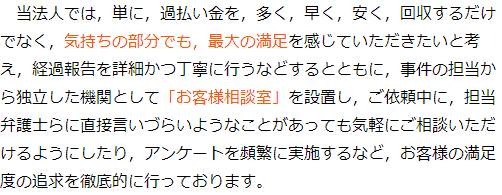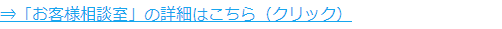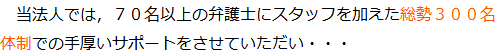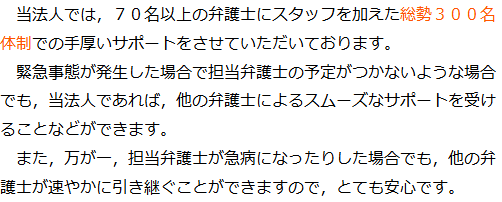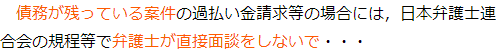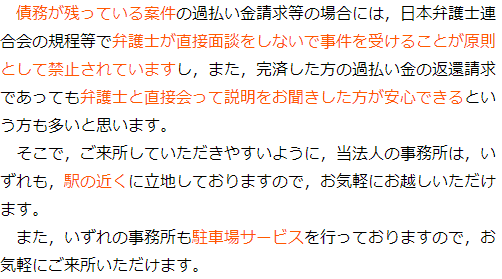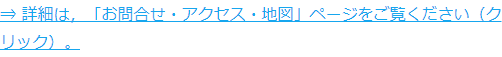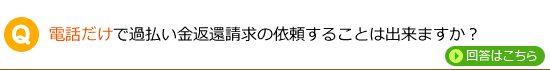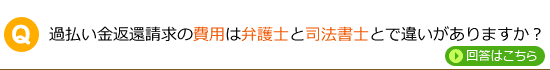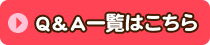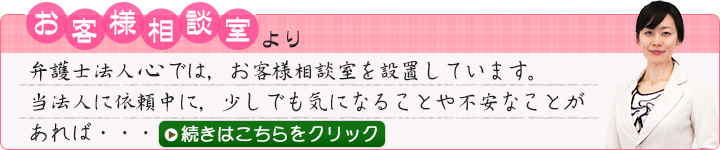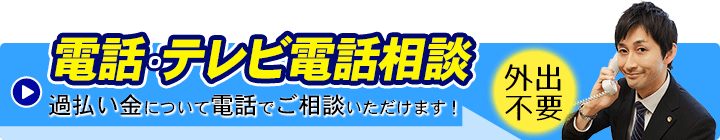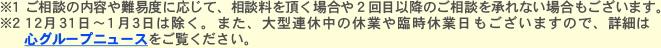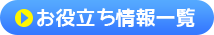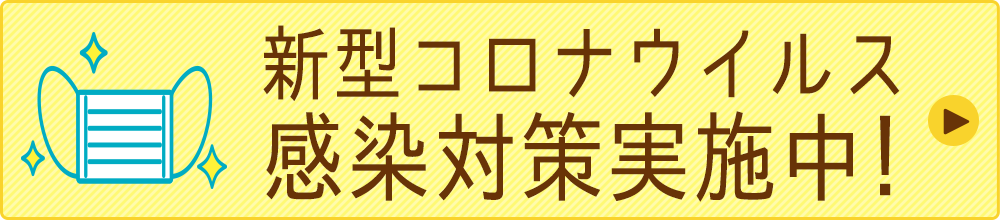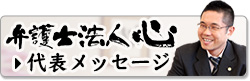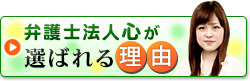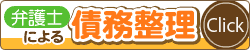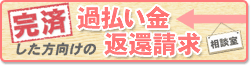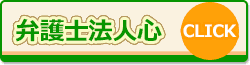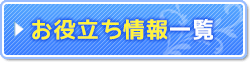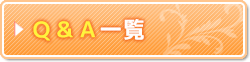四日市の方からのご相談も承ります
借金を完済した方の過払い金につきましては,弁護士と電話相談していただくことが可能です。ご事情があってご来所が難しい方もお気軽にご利用いただけます。
過払い金返還請求における当法人の強み
1 過払い金返還請求について

利息制限法1条1項は、金銭消費貸借について、元本額が10万円未満の場合は年20%、元本額が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本額が100万円以上の場合は年15%を上限と規定し、その超過部分は無効と規定しています。
貸金業者等が前記利息制限法所定の上限を超える利率を設定し、利用者が超える利率で返済していた場合、前記利息制限法所定の利率で利息・元本へ充当していくと(※この作業を「引き直し計算」と言います)、本来支払う義務のない分まで貸金業者に支払っていたことが判明します。
この本来支払い義務のなかったお金の返還を求めるのが、過払い金返還請求です。
なお、利息制限法所定の上限を超える利率でも、有効な返済(※ 「みなし弁済」と呼称されます)となる要件はありますが(最判平成18.1.13等)、非常に厳格な内容であるため、これを満たしていると金融機関側が立証するのは不可能に近いとされています。
2 過払い金返還請求の経験値
多くの事件をこなすことで、事件の見通しを立てやすくなり、かつ、適切な準備を行うことが可能となります。
また、過払い金返還請求に対する金融機関側の対応は、金融機関によって違いがありますが、件数の蓄積によって特徴を把握することが容易となり、最適な対応をとることが可能となります。
当法人は、開業当初から数多くの過払い金返還請求を行ってきており、その豊富な経験に基づいて、事件の最適な進め方を導き出し、実行していくことが可能となっています。
3 論点の把握と説明責任
近年、過払い金返還請求では、金融機関側が請求金額をあっさりと満額で支払ってくることはほとんどありません。
早期解決を前提に、減額での和解をもちかけてくることが非常に多いです。
過払い金返還請求には様々な法的論点があるため、提訴にあたっては、これらの論点について当方に有利な評価をもたらすことができるか、不利な評価をもたらすことにならないか等を検討する必要があります。
当法人では、これらの論点を把握し、依頼者の方に説明責任を果たした上で、提訴する・しないの選択をしていただいており、これにより納得のいく解決を図ることが可能となっています。
過払い金返還請求をするために必要な費用
1 費用の概要
過払い金返還請求を弁護士に依頼する際に必要となる費用は、弁護士報酬と事件処理に要する実費です。
以下では、弁護士報酬と実費に分けて解説します。
2 弁護士報酬について

弁護士報酬は、さらに着手金と成功報酬に分かれます。
着手金は、業務に着手することによって生じる報酬で、通常は契約時にいただきます。
成功報酬は、相手方から過払い金を回収した際に生じる報酬で、回収した過払い金からその分を差し引いて依頼者に返還することが通常です。
請求金額・回収金額のうち、何%を報酬にするかについては、統一的な決まりはないため、法律事務所ごとに違いがあります。
着手金については、あらかじめ依頼者が準備する必要があるため、額によっては負担感が大きくなります。
特に、過払い金返還請求を考える方は、何年も借金に苦しんでこられた方がほとんどのため、十分な資力を有しないことが珍しくありません。
そのため、依頼しやすくするために、事件類型によって着手金をとらず、完全成功報酬制にしている法律事務所は多数あります。
なお、タイムチャージといって、書面作成、電話等での交渉、出廷等といった当該事件の処理に要した時間に応じた報酬を請求するやり方もありますが、過払い金返還請求でこれを採用しているところはほぼないと思われます。
3 実費について
過払い金返還請求の実費は、訴訟をするかどうかによって、大きく変わります。
訴訟提起する場合は、請求額に応じた印紙代(※ 請求金額が大きくなるほど印紙代も高くなる)と出廷費等が発生するため、金額によりますが、数万から数十万円になる可能性があります。
訴訟提起しなければ、電話・FAX・郵送程度のため、数千円で済むことが多いです。
訴訟提起するかどうかは、こちらの請求額と相手の認定額の差、こちらの請求が認められる見込み、先述の実費等を総合考慮の上、最終的には依頼者の方が判断することになります。
4 弁護士法人心における費用設定
過払い金返還請求については、着手金をいただかず、完全成功報酬制で受任しているほか、成功報酬についても比較的低めに設定しています。
過払い金返還請求でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談いただきたいと思います。
手元に資料が残っていない方の過払い金返還請求
1 過払い金返還請求では資料が残っていないケースが多い

過払い金返還請求をする方の大半が、あった方がよい資料の一部しか残っていないか、全く残っていません。
過払い金返還請求をできる方は、主に平成19年以前から取引している必要があり、そこまで昔となると、借入や返済の資料を保管している方は少ないからかと思います。
また、ご家族に知られるのを嫌って、資料を捨ててしまっている方も少なくありません。
2 取引履歴は相手の業者から開示を受けられる
過払い金返還請求には、取引履歴という、いついくら借りて、いついくら返したという履歴が必要です。
ただ、これは相手の業者から開示を受けることができます。
消費者金融やクレジットカード会社は、借入していた方から取引履歴の開示請求を受けた場合は、開示しなければならないと最高裁判所の判決で認められています。
違反した業者は監督官庁から行政処分を受ける可能性もありますので、基本的に所持している取引履歴は開示します。
3 カードや契約書類がなくても返還は受けられる
過払い金返還請求にあった方がよい資料として、相手の業者の借入や返済に使ったカードや契約書類があります。
これらは、法律上の争いがあるケースでこちらに有利な証拠として利用できることがありますが、なければ過払い金の返還を請求できないというものではありません。
4 相手の業者が分からない場合の対応
過払い金返還請求では、取引履歴を取り寄せるときにどこの業者から借入していたかを知る必要があります。
何年も前に完済した方や、亡くなったご両親の過払い金を請求する方で、どこの業者から借入していたか分からないという方もいらっしゃいます。
このように相手の業者が分からない場合、記憶の範囲内で取引履歴の開示を請求するか、通帳の入金・出金に表れていないか、請求書が届いていないか見る方法があります。
また、信用情報機関という、どの業者から借入・延滞・完済しているか等を管理している機関がありますので、信用情報機関から信用情報を取得することも考えられます。
5 資料を保管していない方もご相談ください
過払い金返還請求は、手元に何の資料もなくとも、相手の業者から取引履歴が取得できれば請求可能です。
資料を保管していない方も、お気軽に弁護士までおたずねください。
どうして過払い金が発生するのか
1 過払い金が発生した理由
過払い金は、消費者金融やクレジットカード会社が、以前は法律で認められた、より高い利息をとっていたことで、借りていた方が利息を払いすぎるという事態が起こっていたために発生します。
以下で、もう少し詳しい経緯を見ていきます。
2 グレーゾーン金利の存在

利息制限法では、借入額10万円未満で上限金利20%、10万円以上100万円未満で上限金利18%、100万円以上で上限金利15%と定めています。
一方、平成22年改正前の出資法では、刑事罰を科される利率は29.2%を超えるものとされていました。
また、平成18年12月以前の貸金業法では、20%~29.2%の間の金利は、様々な条件や書類がそろっていれば有効とみなされる(みなし弁済)という規定がありました。
この利息制限法では無効であるものの、出資法・貸金業法では有効とみる余地がある20~29.2%の金利は、「グレーゾーン金利」と呼ばれ、多くの貸金業者がこの利率で貸付を行っていました。
3 みなし弁済は事実上認められなくなった
最高裁平成18年1月13日判決で、通常の貸金業者が使っていた契約書類では、みなし弁済が認められるケースは事実上なくなりました。
これにより、今までグレーゾーン金利で貸し付けていた消費者金融やクレジットカード会社に対して、利息制限法上の上限金利(15~20%)を超えて払いすぎた利息を返してほしいという請求が急増しました。
これが過払い金返還請求です。
4 貸金業者の利率の引き下げと出資法の改正
最高裁平成18年1月13日判決と平成18年12月の貸金業法改正を受けて、平成19年頃から貸金業者は利息制限法の上限金利である15~20%以下に金利を引き下げるようになりました。
そして平成22年に出資法の上限金利も引き下げられ、以降の新規の貸付では過払い金は発生しなくなっています。
5 現在も過払い金返還請求できる場合がある
このように、平成22年以降に新たに借り入れた場合は過払い金が発生しなくなりましたが、主に平成19年以前からキャッシングをしていた方の場合、現在でも過払い金返還請求ができる方は大勢いらっしゃいます。
過払い金があるかもしれないと少しでもお考えの方は、お気軽に弁護士までおたずねください。
過払い金返還請求について専門家を選ぶ際のポイント
1 過払い金返還請求の専門家には、司法書士と弁護士がいる

過払い金返還請求は、利息制限法が定める利率より高い利息でお金を貸していた消費者金融やカード会社に対し、払いすぎた利息を返してもらう手続きです。
過払い金返還請求の専門家には、司法書士と弁護士がいます。
司法書士に依頼するメリットは、弁護士より費用が安いケースがあることです。
デメリットは、過払い金額が140万円以下の場合しか交渉することができないため、過払い金額によっては、司法書士に依頼しても別途弁護士に依頼し直さなければならなくなるケースがあることです。
また、過払い金を取り返すために裁判をする場合、裁判の専門家は弁護士ですから、作成する文書や訴訟活動を通じて、過払い金額に大きな差が出る場合が珍しくありません。
2 過払い金返還請求の経験が豊富な弁護士かどうか
過払い金の返還請求は、相手の消費者金融やカード会社の特徴によって、対応が大きく異なります。
裁判をせず話し合いでも多くの額を返還してくれるかわりに返還時期が遅い業者や、裁判をしなければわずかな額しか返還してくれない業者、倒産寸前で話し合いに応じない業者など様々です。
また、毎年のように過払い金に関する新しい裁判例が出ますので、相手の業者も裁判例を見て対応を変えてきます。
そのため、弁護士側も日々過払い金返還請求をして、相手の業者の変化に応じた対応ができる必要があります。
3 過払い金返還請求にかかる費用が明確かどうか
過払い金返還請求をするのに必要な費用が明確になっているかどうかも、専門家を選ぶ上で大きなポイントです。
弁護士の費用には、着手金、成功報酬、手数料等様々な名目があり、過払い金をとれなかった場合もかかる費用か、過払い金をとれたときにかかる費用か等が異なります。
過払い金を請求して費用倒れにならないように、弁護士に払う費用が分かりやすいかが重要です。
4 ご自宅の近くに事務所の支店があるかどうか
過払い金返還請求は、裁判する場合は、お住まいを管轄する簡易裁判所又は地方裁判所で行うのが一般的です。
遠方にしか支店がない法律事務所に依頼すると、弁護士が裁判所に行く際の費用が高くつくことがあります。
また、法律上の争いがあるケースでは、ご自宅の近くの法律事務所であれば打ち合わせがしやすいので、ご自宅の近くに事務所の支店があることもポイントです。
過払い金が発生する仕組み
1 利息制限法上の上限金利を上回る利息が払いすぎ

過払い金の返還請求は、利息を払いすぎているのを返してもらうという手続きです。
利息制限法では、元本10万円未満は年利20%、10万円以上~100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%を上限と定めています。
現在は、この利率を超えるものは、貸金業者では通常存在せず、ヤミ金融等違法な金融屋や個人間の貸し借りぐらいものです。
では、この利息の払いすぎというのはなぜ起こったのでしょうか。
2 出資法の上限金利の移り変わりとグレーゾーン金利
出資法は、一定の利率を超える場合に刑事罰を科しています。
昭和の頃には年利40%を超える利率も許容されていたようですが、平成3年11月1日から年利40.004%が出資法の上限となり、平成12年6月1日からは年利29.2%が上限となりました。
これでも年利29.2%から利息制限法の上限利率20%までの間は無効な利率のはずですが、刑事罰は課されず、多くの消費者金融やクレジットカード会社がこの間の利率で貸付を行ってきました。
この間の利率をグレーゾーン金利と呼んでいました。
3 最高裁平成18年1月13日判決により広く過払い金請求が可能になった
グレーゾーン金利での貸付が多かったのは、20%~29.2%の間の取引も、貸金業法が定める様々な要件を満たせば有効になる余地があると解釈されていたためです。
ただ、最高裁平成18年1月13日判決は、期限の利益の喪失条項(返済が遅れれば一括請求できるという条項)が入っている契約に基づく貸付で、グレーゾーン金利のものを幅広く無効と判断しました。
これにより、グレーゾーン金利でお金を借りていた方が払い過ぎていた利息を返してもらう「過払い金返還請求」という手続きが、広く可能になったのです。
4 平成22年のグレーゾーン金利の解消
平成22年6月18日施行の出資法改正で、出資法と利息制限法の上限利率は一致するようになり、グレーゾーン金利がなくなりました。
これにより、平成22年以降の貸金業者との取引では過払い金が発生しないことが確実になりました。
ただ、平成19年頃から貸金業者は、自主的に利息制限法の上限利率以下での貸付を行うようになっていましたので、実際は、平成20年以降に借入を始めた方は、過払い金がないケースがほとんどです。
過払い金を払ってこない業者からの取立方法
1 多くの業者は話し合いをまとめれば払ってくる

過払い金返還請求の相手は、消費者金融かカード会社になります。
大手の消費者金融やカード会社は、弁護士との間で、いついくらを返すという金額と時期の話し合いがつけば、基本的にはその約束どおりに支払ってきます。
話し合いがまとまったのに支払わなければ、遅延損害金がついたり、差押えを受ける等で余計負担が大きくなるということを、業者は知っているからです。
しかし、一部の業者は、話し合いがまとまっても約束どおり払わなかったり、そもそも話し合いに応じないこともあります。
ここでは、弁護士が過払い金を強制的に取り立てる方法のうち、3つを記載します。
2 預金の差押え
差押えというのは、強制的に相手の財産から過払い金を取り立てることをいいます。
預金の差押えは、相手の業者の口座の預金を差し押さえる方法です。
これは、基本的に相手の業者がどこの銀行のどこの支店に口座を有しているかの情報をつかまないと、効果があがりません。
当てずっぽうで行っても、口座がなかったり、あっても残高が数百円しかなければ、手続きにかかるお金の方が高くなってしまうからです。
3 現金の差押え
実際に業者の店舗に行って、店舗にある現金を差し押さえる方法です。
執行官という裁判所の職員と一緒に日時を決めて店舗に行き、金庫やレジに入っているお金をもらうことになります。
4 債権の譲渡と相殺
差し押える財産が見つからないときには、その貸金業者に借金をしている方に、過払い金返還請求権を譲渡して買い取ってもらう方法もあります。
たとえば、貸金業者Aに過払い金60万円を返してもらう権利をもつBさんが依頼者であるとき、Aから50万円借りているCさんに対し、過払い金を返してもらう権利を20万円で売るとします。
Cさんは、60万円の債権と自身の50万円の債務(借金)を相殺すると、20万円支払うことで50万円の借金を返さなくてよくなります。
Bさんは、過払い金60万円のうち20万円を回収することができます。
この方法をとる場合、Cさんのような適切な人を見つけてくる必要があります。
5 相手が倒産してしまう前に回収する必要がある
過払い金を約束どおり支払わない業者は、経営状態が悪い業者が多いです。
本当に相手の業者が倒産してしまうときには、差押えする預金や現金も残っておらず、強制的にとろうとしてもほとんど費用倒れになってしまいます。
ですから、過払い金の回収は、早く始めるに越したことはないのです。
過払い金回収にかかる期間
1 過払い金回収にかかる期間を把握するには

主に平成19年以前から、消費者金融やカード会社からのキャッシングをしていた方は、利息制限法が定める利率より高い利息を支払っていたために、過払い金という払いすぎた利息がある可能性があります。
この過払い金の回収にどれくらいの期間がかかるかは、以下の過払い金回収の流れの中で、それぞれの段階においてどのような選択をするかによって変わります。
2 過払い金回収の大まかな流れ
⑴ 取引履歴を取得する
相手の業者から、取引履歴という、いつ・いくら借りて、いつ・いくら返したという取引の記録を取り寄せます。
ここで、おおむね1~2か月かかります。
⑵ 引き直し計算をする
取引履歴をもとに、高すぎる利息で計算されていたものを、利息制限法が認める利息に直して計算し、過払い金がいくらあるかを計算します。
ここで、おおむね2週間程度かかります。
⑶ 話し合いをする又は裁判をする
計算した結果をもとに、相手の業者に何円を返してくださいという請求をし、相手の返答をききます。
このやりとりを何度か繰り返すか、話し合いがつかないなら裁判をして取り返すこともあります。
⑷ 金額と返還時期を合意する
⑶の話し合いに基づき、相手の業者と何円をいつ返してもらうかについて合意をします。
⑸ 過払い金が回収できる
過払い金は、弁護士の預り金口座に振り込まれます。
そこから、弁護士の報酬や実費を差し引いた残額をお返しします。
相手の業者が振り込んでから、実際にお返しするまで、おおむね1~2週間かかります。
3 話し合いや裁判にかかる時間と返還時期による
先ほどの流れの中で、⑶の「話し合い又は裁判をする」と、⑷の「返還時期を合意する」には、期間を書いていません。
なぜなら、⑶と⑷は案件ごとに大きく異なるからです。
⑶の話し合いは早く終わらせるなら2か月程度でまとまりますが、話し合いだけで3,4か月かけることも多いですし、裁判をするなら6か月~1年程度かかることもあります。
また、⑷の返還時期は、金額が決まってから早ければ1か月後、遅ければ1年近く先になります。
早く返してもらうなら金額は少なくなり、じっくり時間をかければ金額が多くなるのが通常で、相手の業者の特徴によるところも大きいです。
4 まずは弁護士にご相談ください
過払い金回収の期間は、早くて6か月程度、遅ければ1年6か月程度が通常で、話し合いを早くで切り上げるか、裁判をするか等については相手の業者の特徴によっても異なります。
特に業者の特徴は、時間が経つと変わるため、過払い金に詳しい弁護士でなければ分かりにくいところですから、詳細は弁護士までおたずねください。
過払い金返還請求をするデメリットと回避の方法
1 過払い金返還請求は完済事案と残有り事案に分かれる

過払い金とは、主に平成19年以前から消費者金融やカード会社から借入をしていた際に、法律で認められたものよりも高い利率で借入をしていたために、払いすぎになっているものをいいます。
この返還を請求することを、過払い金返還請求と言います。
過払い金返還請求のデメリットを考えるうえでは、既に完済している業者に対して過払い金返還請求をする場合と、今も債務が残っている相手方に対して過払い金返還請求をする場合で分けて考える必要があります。
弁護士は、前者を完済事案、後者を残有り事案と呼ぶことが多いです。
2 残有り事案の場合のデメリット
残有り事案は、現在返済中の相手方に対して過払い金返還請求を行うことになります。
この場合、過払い金があるかないかは、相手方から取引履歴をもらう等して調査しなければ正確には分かりません。
過払い金があって、実際返ってくる状態にあることが明らかであればよいのですが、過払い金があっても、債務の方が多くて返済すべきものが残ったり、過払い金が全く発生しない場合もあります。
相手からすれば、残りの債務に対し、弁護士に依頼して約束どおりの返済をしないということになりますので、信用情報に事故登録される、いわゆるブラックリストに載る可能性があります。
そうすると、相手方とする業者のカードだけでなく、新しくカードが作れない、ローンが組めないなどの影響が生じる可能性が高くなります。
3 完済事案の場合のデメリット
完済事案は、今は債務が残っていない相手方なので、約束どおり返済していないという問題が生じることはありません。
ですから、信用情報が傷つくという心配はありません。
ただし、相手とする業者のカードは、完済事案ならば現在使用していないはずですが、今後使用できない可能性はあります。
4 残有りの場合のデメリットの回避方法
では、残有り事案で信用情報に事故登録されるのを回避するためにはどうすればよいでしょうか。
一つは、完済してから過払い金請求をすることです。
こうすれば、完済事案になりますので、請求をしても問題なくなるというわけです。
二つ目は、過払い金があって返ってくるケースであることが明らかであれば、ブラックリストに載らないと言われていることから、あらかじめご自身で取引履歴を取得して、弁護士が計算する等して過払い金が返ってくるケースであることを確認するという方法があります。
弁護士に過払い金返還請求を依頼した場合の裁判の流れ
1 過払い金は、裁判をして請求する方が多くなりやすい

過払い金を業者から取り返す方法としては、裁判をせず業者との話し合いで取り返す方法と、裁判をして取り返す方法の2つがあります。
一般的には、裁判をしても依頼者の手間はほとんどかかりません。
そして、裁判をした方が、弁護士費用や実費を含めても最終的に獲得する金額は多くなる傾向にあります。
ここでは過払い金返還請求の裁判のおおまかな流れをお伝えします。
2 弁護士が訴状を作成、裁判所に提出
依頼を受けた弁護士は、訴状という書類を作成して、裁判所に提出します。
訴状は、業者から取り寄せた取引履歴や、引き直し計算の結果等を添付して、「〇円過払い金があるから全額を払え」という判決を求める内容の書類になります。
引き直し計算というのは、高すぎる利率を法律で認められた利率に直して計算して、いくら過払い金があるか見る計算のことです。
弁護士は、依頼者と相談して過払い金の返還を求める裁判をすると決めてから、おおむね1週間から2週間程度で訴状を提出します。
3 期日に出廷する
訴状を審査した裁判所は、弁護士が裁判所に行く1回目の期日を1か月程度後の日で決めます。
そして、その期日に、弁護士が裁判所に出廷します。
4 次回期日までに書面作成や報告・相談をする
1回目の期日で、1か月程度先の2回目の期日を決めます。
そして、それまでに弁護士が準備書面という追加で主張する書面を作成したり、依頼者に期日の報告をします。
弁護士は、依頼者と相談して、判決をもらうまで進めるか、業者と何円返してもらう条件で交渉するか等の方針を決めます。
5 和解又は判決後入金へ
業者は、負ければ全額支払わなければならない可能性もあるので、おおむね2回~4回程度の期日で、裁判をする前より多くの金額を返す旨の提案をしてきます。
裁判後も、話し合いをして和解で終了することもありますし、全部勝訴の可能性が高ければ期日を重ねて判決をもらうこともあります。
入金は、和解の場合、和解した日からおおむね1~4か月程度、判決の場合は判決日から1か月程度で行われるのが一般的です。
裁判を始めてから入金までは、おおむね3か月~1年くらいかかります。
いずれにせよ、裁判は弁護士・業者・裁判所の間で進むので、ご本人が裁判所に行ったり、ご自分で書類を作成しなければならないことは、ほぼありません。
6 裁判を怖がる必要はありません
裁判というと、何となく怖いとか、大変という印象をお持ちの方もいらっしゃいます。
しかし、過払い金に関しては、こちらが返してもらう側であり、特に責められるものでもありません。
弁護士が出廷から書類作成まで行いますので、ご本人が行うのは、基本的には弁護士の報告・相談を聞いて、どこまで続けるかを決めるくらいです。
裁判の流れ等はお気軽に弁護士までおたずねください。
過払い金があるかどうかわからない方へ
1 過払い金とは

過払い金とは、平成22年以前に、利息制限法と出資法で異なる上限利率が認められており、出資法には反しないが利息制限法に定める上限利率を超える高い利率でお金を借りていた場合に、利息が払いすぎになっているものをいいます。
利息制限法の上限利率は、借入額によって異なりますが、15~20%です。
過払い金があるかどうかは、正確には取引履歴を貸金業者に出してもらわなければ分かりませんが、ここでは過払い金があるかを大体で見分ける簡単な方法をお伝えします。
2 平成19年以前から借入があること
まず、過払い金があるためには、利息制限法の上限利率を超える高い利率で借入をしている必要があります。
法律で利息制限法と出資法の上限が統一されたのは平成22年ですが、それ以前でも、消費者金融やカード会社等の貸金業者は、自主的に利息制限法の上限利率を超えない範囲内の利息で貸し出すようになった時期があります。
その時期は、おおむね平成18年~20年頃です。
平成18年の最高裁判所の判決で、利息制限法違反の貸付は、ほぼ全て違法であると認められました。
この判決を受けて、大手の消費者金融やカード会社は、それまで利息制限法を超える利率で貸していたのを、利息制限法の範囲内にまで引き下げるようになりました。
この対応は、ほとんどが平成19年中に終了していますので、平成19年以前から借入をしている場合でなければ、利息制限法の範囲内の利率であるため、過払い金は発生しません。
3 消費者金融又はカード会社のキャッシング(借入)であること
利息制限法の上限利率を超える高い利息で貸していたのは、基本的に消費者金融とカード会社です。
銀行のカードローンや住宅ローン、車のローン等では、昔からこのような高い利息の商品はなかったことから、銀行のカードローンや、車のローン等を何年払っても過払い金は発生しません。
これは、カード会社の買い物のリボ払いにも当てはまります。
ですので、過払い金があるためには、消費者金融又はカード会社のキャッシング(借入)でなければなりません。
4 完済から10年以内であること
過払い金は、最終取引から10年たつと、消滅時効の成立により返してもらえなくなるという最高裁判所の判例があります。
今もキャッシングの債務が残っている方は、基本的に最後の取引は先月や先々月でしょうから、時効の問題はありません。
しかし、完済している方は、基本的に、完済日が最終取引日ですから、完済から10年たつと時効により過払い金を返してもらうことはできなくなります。
なお、令和2年4月1日以降に取引が終了した借金の場合は、改正民法との関係により、5年で時効にかかる可能性もあります。
ご事情によって異なりますので、まずはお早めには弁護士にご相談ください。